 打印本文
打印本文  关闭窗口
关闭窗口 白蟻(しろあり)
「後生ですわ、お嫂(ねえ)さま。どうかわたしをかばってくださいまし。私を、もうそんなに苦しめないで、承知してくださいましな」
「いいえいいえ、私にはできません。それはどうあってもできないことです」と滝人が、無性にいきばって首を振っているうちに、あの焔に勢いを添えようとするものが、いよいよ猛り立ってきた。すると、時江の声が、それなりちょっと杜絶えたかと思われたが、やがてぞくぞくと震えだしてきて不審なことに、彼女は酔いしれたように上気してしまった。
「いいえ、もうおっしゃらないでください。私、お嫂(ねえ)さまに、一つの証を立てますわ。鉄漿(はぐろ)をつけます。かねてお嫂さまのお望みどおりに、私、鉄漿をつけますわ。そして、お嫂さまと一緒に、どこへなりと、お好きな夢の国にまいりますから……」
そして、相手が何も云わぬのに、独(ひと)り合点(がてん)して、いつか滝人が忘れていった、早鉄漿(はやがね)の壺に鏡を取り出してきた。そして立膝(たてひざ)にした両足を広く踏み開き、小指にちょんぴりとつけた黒い脂(あぶら)で、前歯に軽く触(さわ)ると、時江はその一点の斑(まだら)にさえ、自分の裸身を見るような驚異を感じた。それが秘密な部分にある黒子(ほくろ)みたいで、ちょっと指先で持ち上げたいような、可笑(おか)しさはあったけれども、やがてその黒い斑点が拡がりゆくにつれて、時江はハッハッと獣のような息を吐きはじめ、腰から上をもじもじ廻しはじめた。のみならず、一本芯の洋燈(ランプ)は仄暗いけれども、その光が、額から頬にかけて流れている所は、キメをいっそう細やかに見せていた。もう時江は、自分自身でさえも、その媚(なま)めいた空気に魅せられてしまって、鉄漿(かね)をつける小指の動きを、どうにも止めようがなくなってしまった。しかし、滝人の眼から見ると、そこには魔法のような不思議な変化が現われていったのである。
と云うのは、白と灰色とで段だらにした格子の間を、真黒に塗り潰してしまうと、その灰色がまったく白ちゃけてしまうのであるが、この場合も、それと同じ色彩の対比であろうか。皓歯(しらは)の輝きが一つ一つ消え行くにつれて、それに取って代った天鵞絨(びろうど)のような斑(まだら)が、みるみる顔一面に滲み拡がっていった。すると、不思議な事には、頬の窪みにすうっと明るみが差し、細やかな襞(ひだ)や陰影が底を不気味に揺り上げてきて、わずかに耳の付け根や、生え際のあたりにだけ、病んだような微妙な線が残されるばかりになった。そうして、隆起したくびれ肉からは、波打つような感覚が起ってきて、異様に唆(そそ)りがちな、まるで繻子(しゅす)のようにキメの細かい、逞(たくま)しい肉付きの腰みたいに見えた。滝人は、もうどうすることもできず、見まいとして瞼(まぶた)を閉じた。すると、また暗黒の中で、それが恐ろしくも誇張された容(かたち)となって現われ、今や十四郎のありし日の姿が、その顔の中に永久住んでゆくかのごとく思われるのだった。そうした、とうてい思いもつかなかった喜ばしさの中で、なぜか滝人は、ぞくぞく震えていたのである。身も心も時江に奪われて、十四郎そっくりの写像が、眼前にちらつくのを見ると、そうして生れた新しい恋愛に、彼女の心は、一も二もなく煽り立てられた。滝人は、もう前後が判らなくなってしまったが、絶えずその間も、熱に魘(うな)されて見る、幻影のようなものがつき纏(まと)っていて、周囲の世界が、しだいに彼女から飛びさるように思われると、そのまま滝人は、狂わしい肉情とともに取り残されてしまったのである。が、その時、残忍な狡猾な微笑が、頬に泛(うか)び上がってきて、滝人の顔は、以前どおりの険しさに変ってしまった。それはちょうど、悪狡(わるがしこ)い獣が耳を垂れ、相手が近づくのを待ち構えているようであった。ところが、その図星が当って、鉄漿(はぐろ)をつけ終り、ふと滝人の顔を見ると、その瞬間時江は、喪心したようにクタクタになってしまった。彼女には、もうとりつく島もないではないか。嫂(あね)の気持を緩和しようとしたせっかくの試みが、それでさえいけないのだったら、いったい彼女はどうしたらいいのだろう。いつか、兄夫婦の間に始まるであろう争(いさか)いの余波が、彼女にどのような惨苦をもたらすか、知れたものではないのである。すると時江には、もうこのうえ手段と云って、ただ子供のように嫂(あね)の膝に取り縋(すが)り、哀訴を繰り返すよりほかにないのだった。
「それではお嫂(ねえ)様、私に教えてちょうだい。そのお顔を柔らかにしてから、私がどうすればいいのか、教えてちょうだい」
「ああ十四郎、貴方はそこに……」と時江の声が、耳に入ったのか入らぬのか、滝人の眼に、突然狂ったような光が瞬(またた)いた。すると、(以下七四字削除)本能的にすり抜けたが、(以下六〇一字削除)異様な熱ばみの去らない頭の中で、絶えず皮質をガンガン鳴り響かせているものがあった。滝人は、いつのまにここへ来てしまったのか、自分でも判らないのであるが、そうして、永いこと御霊所の前で髪を乱し瞼を腫れぼったくして、居睡っているように突っ立っていた。
三、弾左谿(だんざだに)炎上
ついにあの男が、鵜飼十四郎に決定されたばかりでなく、**********************、滝人はまるで夢みるような心持で、自分の願望のすべてが充されつくしたのを知った。そして、しばらく月光を浴びて、御霊所の扉に凭(もた)れ掛かっているうちに、しだいとあの異様な熱ばみが去り、ようやく彼女の心に、仄(ほの)白い曙(あけぼの)の光が訪れてきた。それはちょうど、あの獣的な亢奮のために、狂い出したように動き続けていた針が、だんだんに振幅を狭めてきて、最後にぴたりとまっすぐに停まってしまったようなものだった。すると、その茫漠とした意識の中から、なんとなく氷でも踏んでいるかのような、鬱然とした危懼(きぐ)が現われてきた。と云うのは、最初に高代という言葉を聴いたのは、まだ十四郎が意識のはっきりせぬ頃の事であり、その後に時江が耳にしたのも、御霊所の中であって、やはり十四郎は、同じ迷濛状態にあったのではないか。それは、たしかに一脈の驚駭だった。そうして、滝人の手は、怯(おび)やかされるまま、御霊所の扉に引き摺られていったのである。
扉を開くと滝人の鼻には、妙にひしむような、闇の香りに混じって、黴(かび)臭い、紙の匂いが触れてきた。彼女は入口にしばらく佇(たたず)んでいたが、気づいて、頭上の桟窓をずらせた。すると、乳色をした清々(すがすが)しい光線が差し込んでき、その反映で、闇の中から、梁(はり)も壁も、妙に白ちゃけた色で現われてきて、その横側がまた、艶々(つやつや)と黝(くろ)ずんで光っているのだった。眼の前には、二本の柱で区画された一段高い内陣があって、見ていると、その闇が、しだいにせり上がって行くかと思われるほど、框(かまち)は一面に、真白な月光を浴びていた。またその奥には、さまざまな形をした神鏡が、幾つとなく、気味悪い眼球のように閃(きらめ)いているが、背後の鴨居には、祝詞(のりと)を書きつらねた覚え紙が、隙間なく貼り付けられていて、なかには莫大な、信徒の寄進高を記したものなどもあった。滝人は、そこに手燭を発見したので、ようやく仄(ほの)暗い、黄ばんだ光が室内に漂いはじめた。しかし、滝人には、一つの懸念があって、明るくなるとすぐに、内陣の神鏡を一つ持ってきた。そして、机を二つばかり重ねて、その上に神鏡を据え、しきりと何かの高さを、計測しているようであったが、やがて不安げに頷(うなず)くと、背後の祝詞文に明かりを向けた。そして、自分は神鏡の中を覗き込んだのだが、その瞬間、彼女の膝がガクリと落ちて、全身がワナワナ戦(おのの)きだした。
その神鏡の位置というのは、常に行(ぎょう)を行う際に、くらが占めている座席であり、かつまたその高さが彼女の眼の位置だとすれば、当然それと対座している十四郎との関係に、なにか滝人を、使嗾(しそう)するものがあったに相違ない。事実、滝人はそれによって、今度こそは全然償(つぐの)う余地のない、絶望のまっただ中に叩き込まれてしまった。それが、滝人の疑惑に対して、じつに、最終の解答を応えたのである。それから滝人は、刻々血が失われていくような、真蒼な顔をしながら、その結論を、心の中の十四郎に云い聴かせはじめた。
「私は、自分の浅墓(あさはか)な悦(よろこ)びを考えると、じつに無限と云っていいくらい、胸の中が憐憫(あわれみ)で一杯になってしまうのです。お怨みしますわ――この酷(ひど)い誓言を私に要求したのが、ほかならぬ貴方(あなた)なのですから。あの獣臭い骸(むくろ)だけを私に残しておいて、いずこかへ飛び去っておしまいになり、そのうえご自分の抜骸(ぬけがら)に、こんな意地悪い仕草(しぐさ)をさせるなんて、あまりと云えば皮肉ではございませんか。今までも、ときおり貴方の小さな跫音(あしおと)を聴いて、私は何度か不安になりましたけれども、いよいよ今日という今日は、貴方の影法師をしっかと見てとりました。救護所で発した高代という言葉は、まさしく不意の明るみが因(もと)で、鵜飼の腸綿(ひゃくひろ)から放たれたものに相違ございません。そして、いま時江さんが耳にしたものは、貴方が催眠中、お母様の瞳に映った文字を読んだからなのです。ねえこれと同じ例が、仏蘭西(フランス)の心理学者ジャストローの実験中にあるではございませんか。催眠中には、瞳に映った一ミリほどの文字でも読むことができるのです。振り返って、背後を御覧あそばせ。『反玉足玉(かえしたまざたちたま)高代道反玉(たかしろのみちあかしたま)』とある――その中の高代(たかしろ)の二字が、お母さまの瞳に映ったのですけど、文字力のない現在の十四郎には、それを高代(たかよ)と読む以外に術(すべ)はなかったのです。ねえ、そうでございましょう。心の中でそれと判ってはいても、意地悪な貴方は、わざと私にはそれと告げず、さんざん弄(もてあそ)んだ末に……、ええ判りましたとも、あの十四郎には、やはり以前の貴方が住んでいるということも。そして、現在生きているはずの鵜飼邦太郎は、あの時、貴方の顔に似て、死んで行ったということも……」
それから滝人は、逃げるようにして御霊所を出たが、しばらく扉際に立って、濡れた両手を顔に押し当てていた。彼女は、世界中の嘲りを、いまや一身にうけているような気がした。運命とは元来そうしたものだとは云え、あの逆転はあまりに咄嗟(とっさ)であり、あまりに芝居染みて仕組まれているではないか。そして、先刻(さっき)の獣的な歓喜は、またなんという皮肉な前狂言だったのであろう。滝人は、知らぬ男の前で着物を脱がされたような、恥かしさと怖ろしさで一杯になりながら、月夜の庭を不確かな足どりで、当てどもなく彷徨(さまよ)いはじめた。舌が真白に乾いて、胸は上から、重いもので圧(おさ)れているように重たかった。頭の中で、ズキリズキリと疼き上げているものがあって、絶えずたぎっているような血が、顳※(こめかみ)から心臓にかけて、循環しているのが判るような気がした。滝人は、絶えず落ち着こうと努めていた。そして、何か忘れてはならないものを、忘れているのではないかと思ったり、突然自分には、とうてい判断がつかぬような、観念に打たれて驚かされることもあった。しかし、そういう無自覚の間にも、絶えず物を考えようとする力が、藻掻(もが)き出てくるのだったが、それはほんの瞬間であって、再び鈍い、無意識の中に沈んでしまうのだった。そうしているうちに、湯気のようなものを裾(すそ)暖かに感じたかと思うと、突然烈しい苦痛が下から突き上げてきた。彼女はいつのまにか土間の閾(しきい)を踏み跨(また)いでいて、その両足の下に、仔鹿(かよ)の生々しい血首をみた。その瞬間一つの恐ろしい観念が、滝人を波濤(はとう)のように圧倒してしまった。身にも心にも、均衡を失ってしまって、思わず投げ出されたように、地面に這いつくばった。そして、頬を草の根にすりつけ、冷々(ひえびえ)とした地の息を嗅ぎながら、絶えず襲い掛かってくる、あの危険な囁きから逃れようと悶(もだ)えた。
そこには、腐爛しかかった仔鹿(かよ)の首から、排泄物のような異臭が洩れていて、それがあの堪えられぬ、産の苦痛を滝人に思い出させた。しかし、現在の十四郎が、真実の変貌という事になってしまうと、あの物凄い遊戯をしてまで、時江に植えつけた美しい幻像は、いったいどうなってしまうのであろう。二人の十四郎――そこで滝人は、たちまちどうにも抜き差しのならない疑題に直面してしまった。すると、しんしんとあの歓喜が舞い戻ってきて、暗い光明のない闇の中から、パッと差し込んできた一条の光があった。滝人は、まるで夢魔に襲われたような慌(あわ)てかたで、すっと立ち上がった。この孤独な地峡の中で、甲斐(かい)のある生存を保っていくには、何よりあの腫物(はれもの)を除かねばならない。あの美醜の両面は、それぞれに十四郎の、二つの人生を代表している。けれども、その二つを心の上に重ねてゆくとするには、あまりに鉄漿(はぐろ)をつけた時江が、十四郎そのものであり(以下二三七字削除)現在の十四郎には生存を拒まねばならない――その物狂わしさは、倒錯などというよりも、むしろ心の大奇観だったであろう。まったく、この不思議な貞操のために、滝人はある一つの、恐ろしい決意を胸に固め、十四郎のために、十四郎を殺さねばならなくなってしまったのである。しかし、そうなると、たとえ十四郎だけを除いたにしても、それに続いて、なお喜惣が舌なめずりしているのを考えねばならなかった。さらにその二人が除かれたにしても、その間の関係を知り尽している母のくら――いやその舌が、なおその背後に待ち構えているのも忘れてはならない。すると、その三重の人物が、滝人の頭の中で絡み合ってきて、それをどういうふうに按配(あんばい)したらいいのか――そうしてしばらくのあいだ、それぞれに割付けねばならない、役割の事で悩まねばならなかった。しかしそのようにいろいろな考えが、成長しては積り重なってゆくうちに、どれもこれも纏(まと)まりのつかない、空想的な形に見えだしてきたが、そのうち、突然に彼女は、がんと頭を撲(う)たれたような気がした。そして、思わず眼が昏(くら)むのを覚えた。
今まであの隧道(とんねる)の惨事以来、彼女に絶えず囁(ささや)きつづけていた、高代(たかよ)という一事が、今度も滝人の前に二つ幻像となって現われた。それは、最初鵜飼の腸綿(ひゃくひろ)の中に現われて以来、あるいはくらの瞳の中に映ったり、また数形式(ナンバー・フォームス)の幻ともなって、時江を脅(おびや)かした事もあった。けれども、いよいよ最後には二つの形をとり、滝人の企てを凱歌(がいか)に導こうとしたのである。漠として形のない、心の像のみで相手を斃(たお)す――それは、誰しも望むべくして得られない、殺人の形式として、おそらく最高のものではないか。
午後の雷雨のために、湿気が吹き払われたせいか、山峡の宵深くは、真夏とも思われぬ冷気に凍えるのを感じた。頭上に骨っぽい峰が月光を浴びて、それが白衣を着た巨人のように見え、そのはるか下に、真黒な梢を浮き上がらせている樅(もみ)の大樹は、その巨人が引っさげている、鋭い穂槍のように思えた。それは、頭の病的なときに見る夢のようであって、ともすると、現実に引き入れたくなるような奇怪な場面であった。しかし、それから母屋のなかに入り、その光景を桟(さん)窓越しに眺めている滝人には、いささかもそうした物凄い遊戯が感じられず、まったくその数瞬間は、緊張とも亢奮とも、なんともつかぬ不安の極点にあった。ところで、滝人が最初目(もく)した、十四郎の居間付近について、やや図解的な記述が必要であると思う。その寝間というのは、蚕室の土間の階段を上った右側にあって、前の廊下には、雨戸の上が横に開閉する、桟窓があった。そして、廊下から以前の階段を下った所は、大部分を枯草小屋が占めているので、自然土間が鍵形になり、一方は扉口に、もう一つのやや広い方は、階段と向き合った蚕室に続いていて、そこにも幅広い、手縁(てべり)をつけた階段があり、その上方が蚕室になっていた。しかし、その二つの階段は、向き合っているとはいえ、蚕室の方は、両側に手縁があるだけ……壁に寄った方の手縁の端から直線を引いてみると、それが向う側では、階(きざはし)の中央辺に当るのだった。しかし、そのような事物の位置一つに、十四郎の死地が口を開いていたのである。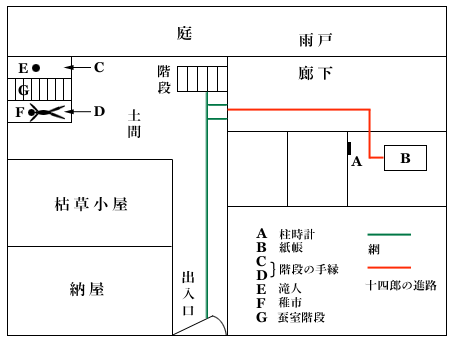
それから滝人は永いこと、蚕室の階段に突っ立っていた。そしてじっと神経を磨ぎ澄まし、何か一つの物音を聴き取ろうとするもののようであった。そこは、空気の湿りを乾草が吸い取ってしまうためか、闇が粘(ね)とついたようにじめじめしていて、時おり風に鳴ると、枯草が鈴のような音を立てる。しかし、滝人の足元には、もう一つ物音があって、彼女は絶えずそれに眼を配り、少しでも遠ざかると紐を手繰(たぐ)っては、何か人馴れた生物のようなものを、扱っていた。それが、唖(おし)の変形児稚市(ちごいち)だったのである。が、それを見ると、滝人は吾が児(こ)までも使い、夫の死に何かの役目を勤めさせようとするのであろう。しかし、その間滝人は、いつものような内語を囁きつづけていた。
「貴方(あなた)、私はあの醜い生物(いきもの)を、これから絞首台に上(のぼ)させようとするのです。もし人格と記憶が生存の全部だといたしますなら、死後の清浄という意味からでも、私をお咎(とが)めにはなりますまいね。いいえ、これで貴方は、まったく清らかになれるのですわ。稚市に芽ばえたものを、やはり終いにも、この子が刈り取ってくれるのですから、もうすぐと、あの生物の眼には、高代という魔法の字が映るに相違ないのです。どこにでしょうか。しかもそれは、二度現われるはずなのです。ときに、『反転的遠景錯覚(イリュージョン・オブ・リヴァシブル・パースペクチヴ)』という、心理学上の術語をご存知でいらっしゃいまして。では、試しに名刺を二つに折って、その内側になったほうを、かしげながら片目で眺めて御覧あそばせな。きっとそれが、折った外側のように見えるはずなのですから。つまり、内角が外角に変ってしまうのですが、いまあの生物は引ん曲った溝を月の山のようにくねらせて、それは長閑(のどか)な、憎たらしい高鼾(たかいびき)をかいておりますの。でも、すぐ眼が覚めて、それからこちらへ、引き摺られるようにやって来るに相違ありませんわ。なぜかって、よくこんなそらぞらしい気持で、私が云えるかって。だって、そうでございましょう。稚市とあの男と、いったいどこが違っておりますの。ただ片方は光に背を向け、あの男の方はそれを慕って、何かの植物のような向光性(トロピズム)があるだけなんですものね。いえ、もうすぐにお判りになりますわ。あの男は、いま紙帳(しちょう)の中で眠っておりますの――下が高簀子(たかすのこ)なものですから、普通の蚊帳(かや)よりもよほど涼しいとか申しまして。そしてその紙帳というのは、祝詞(のりと)文の反古(ほご)を綴(つな)いだものに渋を塗ったのですが、偶然にも高代という二字が、頭と足先に当る両方の上隅に、同じよう跨っているのです。そこで、私が、なぜ前もって桟窓を閉じ、時計の振子を停めたか、その理由を申しましょう。現在あの男は、紙帳の中に眠っているのですが、眼を覚ますと、そこが、紙帳の外であるような感覚が起ってしまうのです。[#「紙帳の中に眠っているのですが、眼を覚ますと、そこが、紙帳の外であるような感覚が起ってしまうのです。」に傍点]いいえ、奇態でも何でもありませんわ。ちょうど具合よく、あの男は仔鹿(かよ)の脂(あぶら)をうけて、右眼が利かないのですし、桟(さん)の間から洩れる月の光が、紙帳の隅の、その所だけを刷いているのですから。当然下は闇ですし、頭を擡(もた)げると、頭上にある高代(たかよ)の二字が、外側へ折れているように見えて、自分が蚊帳の外にいるのではないか――と錯覚を起してしまうのです。ですから、外に出たと思って中に入ろうとし、紙帳の垂れをまくって一足膝行(いざ)ると、今度は反対に外へ出てしまうのですが、その眼の前に、一つの穽(あな)が設(しつら)えてあるのです。以前東京の本殿にございました、大きな時計を御記憶でいらっしゃいましょう。あの下にさがっている短冊形の振子を、先刻(さっき)十一時十分の所で停めておいたのです。そして、紙帳にある高代の二字がそれに小さく映るとしましたら、なんとなく、御霊所の母の眼に似つかわしいではございませんかしら」
滝人はそうしているうちにも、絶えず眼を、十四郎の寝間の方角に配っていて、廊下の仄(ほの)かな闇を潜っている物音なら、どんな些細なものでも、聴き洩らすまいとしていた。しかし、そこには依然として、この地峡さながらのごとく音がなかった。彼女はもう、渾身(こんしん)の注意に疲れきってしまい、その微かな音のない声にも、妙に涸(か)れたような、しわがれが加わってきた。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页 尾页
 打印本文
打印本文  关闭窗口
关闭窗口