*
宿屋や料理屋などの広告に、その庭園や泉石の風景をペンキ絵で描いた建て札のようなものが、よく田舎の道ばたなどに立ててある。
たとえば、その池などが、ちょっとした湖水ぐらいはありそうに描かれているが、実際はほんの金魚池ぐらいのものであったりする。
ああいう絵をかく絵かきは、しかし、ある意味でえらいと思う。
天然を超越して、しかもまたとにかく新しい現実を創造するのだから。
(大正十年十二月、渋柿)
[#改ページ] *
暮れの押し詰まった銀座の街を、子供を連れてぶらぶら歩いていた。
新年用の盆栽を並べた露店が、何軒となくつづいている。
貝細工のような福寿草よりも、せせこましい枝ぶりをした
鉢の梅よりも、私は、
藁で束ねた
藪柑子の輝く色彩をまたなく美しいものと思った。
まんじゅうをふかして売っている露店がある。
蒸籠から出したばかりのまんじゅうからは、暖かそうな蒸気がゆるやかな
渦を巻いて立ちのぼっている。
私は、そのまんじゅうをつまんで、両の
掌でぎゅっと握りしめてみたかった。
そして子供らといっしょにそれを味わってみたいと思った。
まんじゅうの前に動いた私の心の惰性は、ついその隣の紙風船屋へ私を導いて、そこで私に大きな風船玉を二つ買わせた。
まんじゅうを食う事と、紙風船をもてあそぶ事との道徳的価値の差違いかんといったような事を考えながら、また子供の手をひいて暮れの銀座の街をぶらぶらとあてもなく歩いて行った。
(大正十一年二月、渋柿)
[#改ページ] *
祖父がなくなった時に、そのただ一人の女の子として取り残された私の母は、わずかに十二歳であった。
家を継ぐべき養子として、当時十八歳の父が迎えられる事になったが、江戸詰めの藩公の許可を得るために往復二か月を要した。
それから五十日の喪に服した後、さらに江戸まで申請して、いよいよ家督相続がきまるまでにまた二か月かかった。
一月二十七日に祖父が死んで、七月四日に家督が落ち着いたのだそうである。
喪中は座敷に
簾をたれて白日をさえぎり、高声に話しする事も、
木綿車を回すことさえも
警められた。
すべてが落着した時に、庭は荒野のように草が茂っていて、始末に困ったそうである。
(大正十一年四月、渋柿)
[#改ページ] *
安政時代の土佐の高知での話である。
刃傷事件に座して、親族立ち会いの上で詰め腹を切らされた十九歳の少年の祖母になる人が、愁傷の余りに失心しようとした。
居合わせた人が、あわててその場にあった鉄瓶の湯をその
老媼の口に注ぎ込んだ。
老媼は、その鉄瓶の底をなで回した掌で、自分の顔をやたらとなで回したために、顔じゅう一面にまっ黒い斑点ができた。
居合わせた人々は、そういう極端な悲惨な事情のもとにも、やはりそれを見て笑ったそうである。
(大正十一年四月、渋柿)
[#改ページ] *
子猫が勢いに乗じて高い樹のそらに上ったが、おりることができなくなって困っている。
親猫が樹の根元へすわってこずえを見上げては鳴いている。
人がそばへ行くと、親猫は人の顔を見ては訴えるように鳴く。
あたかも助けを求めるもののようである。
こういう状態が二十分もつづいたかと思う。
その間に親猫は一、二度途中まで登って行ったが、どうすることもできなくて、おめおめとまたおりて来るのであった。
子猫はとうとう降り始めたが、脚をすべらせて、
山吹の茂みの中へおち込んだ。
それを抱き上げて連れて来ると、親猫はいそいそとあとからついて来る。
そうして、縁側におろされた子猫をいきなり
嘗め始める。
子猫は、すぐに乳房にしゃぶりついて、音高くのどを鳴らしはじめる。
親猫もクルークルーと恩愛にむせぶように咽喉を鳴らしながら、いつまでもいつまでも根気よく嘗め回し、嘗めころがすのである。
単にこれだけの猫のふるまいを見ていても、猫のすることはすべて純粋な本能的衝動によるもので、人間のすることはみんな霊性のはたらきだという説は到底信じられなくなる。
(大正十一年六月、渋柿)
[#改ページ]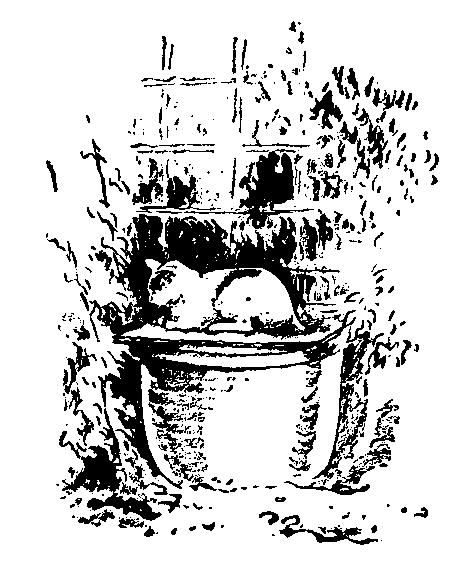 [#改ページ]
[#改ページ] *
平和会議の結果として、ドイツでは、発動機を使った飛行機の使用製作を制限された。
すると、ドイツ人はすぐに、発動機なしで、もちろん水素なども使わず、ただ風の
弛張と上昇気流を利用するだけで上空を
翔けり歩く研究を始めた。
最近のレコードとしては約二十分も、らくらくと空中を翔けり回った男がある。
飛んだ距離は二里近くであった。
詩人をいじめると詩が生まれるように、科学者をいじめると、いろいろな発明や発見が生まれるのである。
(大正十一年八月、渋柿)
[#改ページ] *
シヤトルの
勧工場でいろいろのみやげ物を買ったついでに、草花の種を少しばかり求めた。
そのときに、そこの売り子が
「これはあなたにあげましょう。私この花がすきですから」
と言って、おまけに添えてくれたのが、珍しくもない
鳳仙花の種であった。
帰って来てまいたこれらのいろいろの種のうちの多くのものは、てんで発芽もしなかったし、また生えたのでもたいていろくな花はつけず、一年きりで影も形もなく消えてしまった。
しかし、かの売り子がおまけにくれた鳳仙花だけは、実にみごとに生長して、そうして鳳仙花とは思われないほどに大きく美しく花を着けた。
そうしてその花の種は、今でもなお、年々に裏庭の夏から秋へかけてのながめをにぎわすことになっている。
この一
些事の中にも、霊魂不滅の問題が隠れているのではないかという気がする。
(大正十一年十一月、渋柿)
[#改ページ] *
切符をもらったので、久しぶりに上野音楽学校の演奏会を聞きに行った。
あそこの聴衆席にすわって音楽を聞いていると、いつでも学生時代の夢を思い出すと同時にまた夏目先生を想い出すのである。
オーケストラの太鼓を打つ人は、どうも見たところあまり勤めばえのする派手な役割とは思われない。
何事にも光栄の冠を望む若い人にやらせるには、少し気の毒なような役である。
しかし、あれは実際はやはり非常にだいじな役目であるに相違ない。
そう思うと太鼓の人に対するある好感をいだかせられる。
ロシニのスタバト・マーテルを聞きながら、こんなことも考えた。
ほんとうのキリスト教はもうとうの昔に
亡びてしまって、ただ
幽かな余響のようなものが、わずかに、こういう音楽の中に生き残っているのではないか。
(大正十二年一月、渋柿)
[#改ページ] *
大学の構内を歩いていた。
病院のほうから、子供をおぶった男が出て来た。
近づいたとき見ると、男の顔には、なんという皮膚病だか、
葡萄ぐらいの大きさの
疣が一面に
簇生していて、見るもおぞましく、身の毛がよだつようなここちがした。
背中の子供は、やっと三つか四つのかわいい女の子であったが、世にもうららかな顔をして、この恐ろしい男の背にすがっていた。
そうして、「おとうちゃん」と呼びかけては、何かしら片言で話している。
そのなつかしそうな声を聞いたときに、私は、急に何物かが胸の中で溶けて流れるような心持ちがした。
(大正十二年三月、渋柿)
[#改ページ] *
数年前の早春に、神田の花屋で、ヒアシンスの球根を一つと、チューリップのを五つ六つと買って来て、中庭の小さな花壇に植え付けた。
いずれもみごとな花が咲いた。
ことにチューリップは勢いよく生長して、色さまざまの大きな花を着けた。
ヒアシンスは、そのそばにむしろさびしくひとり咲いていた。
その後別に手入れもせず、冬が来ても掘り上げるだけの世話もせずに、打ち棄ててあるが、それでも春が来ると、忘れずに芽を出して、まだ雑草も生え出ぬ黒い土の上にあざやかな緑色の焔を燃え立たせる。
始めに勢いのよかったチューリップは、年々に
萎縮してしまって、今年はもうほんの申し訳のような葉を出している。
つぼみのあるのもすくないらしい。
これに反して、始めにただ一本であったヒアシンスは、次第に数を増し、それがみんな元気よく生い立って、サファヤで造ったような花を鈴なりに咲かせている。
そうして小さな花壇をわが物のように占領している。
この二つの花の盛衰はわれわれにいろいろな事を考えさせる。
(大正十二年五月、渋柿)
[#改ページ] *
鰻をとる方法がいろいろある。
筌を用いるのは、人間のほうから言って最も受動的な方法である。
鰻のほうで押しかけて来なければものにならない。
次には、
蚯蚓の
数珠を束ねたので誘惑する方法がある。
その次には、鰻のいる穴の中へ釣り針をさしこんで、鰻の鼻先に見せびらかす方法がある。
これらはよほど主動的であるが、それでも鰻のほうで気がなければ成立しない。
次には、鰻の穴を捜して
泥の中へ手を突っ込んでつかまえる。
これは純粋に主動的な方法である。
最後に
鰻掻きという方法がある。
この場合のなりゆきを支配するものは「偶然」である。
(大正十二年六月、渋柿)
[#改ページ] *
無地の
鶯茶色のネクタイを捜して歩いたがなかなか見つからない。
東京という所も存外不便な所である。
このごろ石油ランプを探し歩いている。
神田や銀座はもちろん、板橋
界隈も探したが、座敷用のランプは見つからない。
東京という所は存外不便な所である。
東京市民がみんな石油ランプを要求するような時期が、いつかはまためぐって来そうに思われてしかたがない。
(大正十二年七月、渋柿)
(『柿の種』への追記) 大正十二年七月一日発行の「渋柿」にこれが掲載されてから、ちょうど二か月後に関東大震災が起こって、東京じゅうの電燈が役に立たなくなった。これも不思議な回りあわせであった。
[#改ページ] *
本石町の金物店へはいった。
「開き戸のパタンパタン
煽るのを止める、こんなふうな金具はありませんか。」
おぼつかない手まねをしながら聞いた。
主婦はにやにや笑いながら、「ヘイ、ございます。……煽り留めとでも申しましょうか。」
出して来たボール箱には、なるほど、アオリドメと片仮名でちゃんと書いてあった。
うまい名をつけたものだと感心した。
物の名というものはやはりありがたいものである。
おつりにもらった、穴のある白銅貨の二つが、どういうわけだか、穴に糸を通して結び合わせてあった。
三越で買い物をした時に、この結び合わせた白銅を出したら、相手の小店員がにやにや笑いながら受け取った。
この二つの白銅の結び合わせにも何か適当な名前がつけられそうなものだと思ったが、やはりなかなかうまい名前は見つからない。
(大正十二年八月、渋柿)
[#改ページ] *
道ばたの
崖の
青芒の中に一本の
楢の木が立っている。
その幹に虫がたくさん群がっている。
紫色の紋のある美しい
蝶が五、六羽、蜂が二種類、
金亀子のような
甲虫が一種、そのほかに、大きな
山蟻や
羽蟻もいる。
よく見ると、木の幹には、いくつとなく、小指の頭ぐらいの穴があいて、その穴の周囲の樹皮がまくれ上がりふくれ上がって、ちょうど、人間の手足にできた
瘍のような
恰好になっている。
虫類はそれらの穴のまわりに群がっているのである。
人間の眼には、おぞましく気味の悪いこの樹幹の吹き出物に人間の知らない強い誘惑の魅力があって、これらの数多くの昆虫をひきよせるものと見える。
私は、この虫の世界のバッカスの饗宴を見ているうちに、何かしら名状し難い、恐ろしいような物すごいような心持ちに襲われたのであった。
(大正十二年九月、渋柿)
[#改ページ] *
震災の火事の焼け跡の煙がまだ消えやらぬころ、黒焦げになった樹の幹に
鉛丹色のかびのようなものが生え始めて、それが驚くべき速度で繁殖した。
樹という樹に生え広がって行った。
そうして、その
丹色が、焔にあぶられた電車の架空線の電柱の赤さびの色や、焼け跡一面に散らばった煉瓦や、焼けた瓦の赤い色と
映え合っていた。
道ばたに捨てられた握り飯にまでも、一面にこの赤かびが繁殖していた。
そうして、これが、あらゆる生命を焼き尽くされたと思われる焦土の上に、早くも盛り返して来る新しい生命の胚芽の先駆者であった。
三、四日たつと、焼けた
芝生はもう青くなり、しゅろ竹や
蘇鉄が芽を吹き、
銀杏も細い若葉を吹き出した。
藤や桜は返り花をつけて、九月の末に春が帰って来た。
焦土の中に
萌えいずる緑はうれしかった。
崩れ落ちた工場の
廃墟に咲き出た、名も知らぬ雑草の花を見た時には思わず涙が出た。
(大正十二年十一月、渋柿)
[#改ページ] *
震災後の十月十五日に
酒匂川の仮橋を渡った。
川の岸辺にも川床にも、数限りもない流木が散らばり、引っかかっていた。
それが、大きな樹も小さな
灌木も、みんなきれいに樹皮をはがれて裸になって、小枝のもぎ取られた跡は
房楊枝のように、またささらのようにそそけ立っていた。
それがまた、半ば泥に埋もれて、
脱れ出ようともがいているようなのや、お互いにからみ合い、もつれ合って、最期の
苦悶の姿をそのままにとどめているようなのもある。
また、かろうじて橋杭にしがみついて、濁流に押し流されまいと戦っているようなのもある。
上流の
谿谷の山崩れのために、生きながら埋められたおびただしい樹木が、豪雨のために洗い流され、押し流されて、ここまで来るうちに、とうとうこんな
骸骨のようなものになってしまったのであろう。
被服廠の惨状を見ることを免れた私は、思わぬ所でこの恐ろしい「死骸の
磧」を見なければならなかったのである。
(大正十二年十二月、渋柿)
[#改ページ] *
ある日。
汽車のいちばん最後の客車に乗って、後端の戸口から線路を見渡した時に、夕日がちょうど線路の末のほうに沈んでしまって、わずかな雲に夕映えが残っていたので、
鉄軌がそれに映じて金色の蛇のように輝き、もう暗くなりかけた地面に、くっきり二条の並行線を
劃していた。
汽車の進むにつれて、おりおり線路のカーヴにかかる。
カーヴとカーヴとの間はまっすぐな直線である。
それが、多くは踏切の所から突然曲がり始める。
ほとんど一様な曲率で曲がって行っては、また突然直線に移る。
なるほど、こうするのが工事の上からは最も便利であろうと思って見ていた。
しかし、少なくもその時の私には、この、曲線と直線との継ぎはぎの鉄路が、なんとなく不自然で、ぎごちなく、また不安な感じを与えるのであった。
そうして、鉄道に沿うた、昔のままの街道の、いかにも自然な、美しく優雅な曲線を、またなつかしいもののように思ってながめるのであった。
(大正十三年一月、渋柿)
[#改ページ] *
震災後、久しぶりで銀座を歩いてみた。
いつのまにかバラックが軒を並べて、歳暮の店飾りをしている。
東側の人道には、以前のようにいろいろの露店が並び、西側にはやはり、新年用の盆栽を並べた
葭簀張りも出ている。
歩きながら、店々に並べられた商品だけに注目して見ていると、地震前と同じ銀座のような気もする。
往来の人を見てもそうである。
してみると、銀座というものの「内容」は、つまりただ商品と往来の人とだけであって、ほかには何もなかったということになる。
それとも地震前の銀座が、やはり一種のバラック街に過ぎなかったということになるのかもしれない。
(大正十三年二月、渋柿)
[#改ページ] *
ルノアルの絵の好きな男がいた。
その男がある女に恋をした。
その女は、他人の眼からは、どうにも美人とは思われないような女であったが、どこかしら、ルノアルの描くあるタイプの女に似たところはあったのだそうである。
俳句をやらない人には、到底解することのできない自然界や人間界の美しさがあるであろうと思うが、このことと、このルノアルの女の話とは少し関係があるように思われる。
(大正十三年三月、渋柿)
[#改ページ]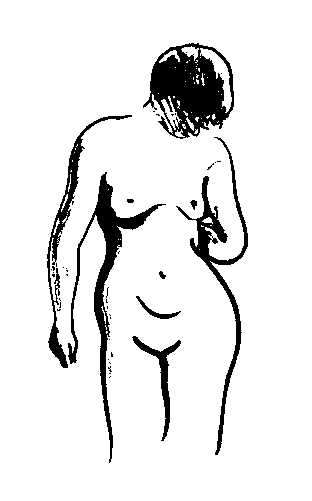 [#改ページ]
[#改ページ] *
夢の世界の可能性は、現実の世界の可能性の延長である。
どれほどに有りうべからざる事と思われるような夢中の事象でも、よくよく考えてみると、それはただ
至極平凡な可能性をほんの少しばかり変形しただけのものである。
してみると、事によると、夢の中で可能なあらゆる事が、人間百万年の未来には、みんな現実の可能性の中にはいって来るかもしれない。
もしそうだとすると、その百万年後の人たちの見る夢はどんなものであるか。
それは現在のわれわれの想像を超越したものであるに相違ない。
(大正十三年四月、渋柿)
[#改ページ] *
日本は地震国だと言って悲観する人もある。
しかし、いわゆる地震国でない国にも、まれにはなかなかの大地震の起こることはある。
そうして、日本ではとても見られないような大仕掛けの大地震が起こることもある。
一九〇六年のサンフランシスコ地震の時に生じた断層線の長さは四百五十キロメートルに達した。
一九二〇年のシナ
甘粛省の地震には十万人の死者を生じた。
考えてみると、日本のような国では、少しずつ、なしくずしに小仕掛けの地震を連発しているが、現在までのところで安全のように思われている他の国では、存外三千年に一度か、五千年に一度か、想像もできないような大地震が一度に襲って来て、一国が全滅するような事が起こりはしないか。
これを過去の実例に徴するためには、人間の歴史はあまりに短い。
その三千年目か、五千年目は
明日にも来るかもしれない。
その時には、その国の人々は、地震国日本をうらやむかもしれない。
(大正十三年五月、渋柿)
[#改ページ] *
晩春の曇り日に、
永代橋を東へ渡った。
橋のたもとに、電車の監督と思われる服装の、四十恰好の男が立っていた。
右の手には、そこらから拾って来たらしい細長い
板片を持って、それを左右に打ちふりながら、橋のほうから来る電車に合図のような事をしていた。
左の手を見ると、一疋の生きた
蟹の甲らの両脇を指先でつまんでいる。
その手の先を一尺ほどもからだから離して、さもだいじそうにつまんでいる。
そうして、なんとなくにこやかにうれしそうな顔をしているのであった。
この男の家には、六つか七つぐらいの男の子がいそうな気がした。
その家はここからそんなに遠くない所にありそうな気がした。
(大正十三年六月、渋柿)
[#改ページ]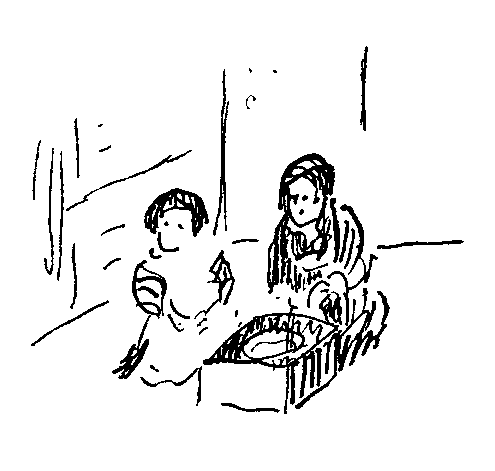 [#改ページ]
[#改ページ] *
三、四年前に、近所の花屋で、小さな鉄線かずらを買って来て、隣家との境の石垣の根に植えておいた。
そのまわりに年々生い茂る
款冬などに負かされるのか、いっこうに大きくもならず、一度も花をつけたことは無かった。
去年の秋の大地震に石垣が崩れ落ちて、そのあたりの草木は無残におしつぶされた。
しかし、不思議につぶされないで助かった鉄線かずらに今度初めて花が咲いた。
それもたった二輪だけ、款冬の葉陰に隠れて咲いているのを見つけた。
地べたにはっているつるを起こして、
篠竹を三本石垣に立て掛けたのにそれをからませてやったら、それから幾日もたたないうちに、おもしろいように元気よくつるを延ばし始めた。
少し離れた所に紅うつぎが一本ある。
去年は目ざましい咲き方をして見せたのに、石垣にたたきつぶされて、やっと命だけは取り止めたが、花はただの一輪も咲かなかった。
(大正十三年七月、渋柿)
[#改ページ] *
大道で手品をやっているところを、そのうしろの家の二階から見下ろしていると、あんまり品玉がよく見え過ぎて、ばからしくて見ていられないそうである。
感心して見物している人たちのほうが不思議に見えるそうである。
それもそのはずである。
手品というものが、本来、背後から見下ろす人のためにできた芸当ではないのだから。
(大正十三年八月、渋柿)
[#改ページ] *
「二階の欄干で、雪の降るのを見ていると、自分のからだが、二階といっしょに、だんだん空中へ上がって行くような気がする」
と、今年十二になる女の子がいう。
こういう子供の頭の中には、きっとおとなの知らない詩の世界があるだろうと思う。
しかしまた、こういう種類の子供には、どこか病弱なところがあるのではないかという気がする。
(大正十三年八月、渋柿)
[#改ページ] *
白山下へ来ると、道ばたで馬が倒れていた。
馬方が、バケツに水をくんで来ては、馬の頭から腹から浴びせかけていた。
頸のまわりには大きな氷塊が二つ三つころがっていた。
毎年盛夏のころにはしばしば出くわす光景である。
こうまでならないうちに、こうなってからの手当の十分の一でもしてやればよいのにと思うことである。
曙町の、とある横町をはいると、やはり道ばたに荷馬車が一台とまっていた。
大きな葉桜の枝が道路の片側いっぱいに影を拡げている下に、馬は涼しそうに休息していた。
馬にでも地獄と極楽はあるのである。
(大正十三年九月、渋柿)
[#改ページ]
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页 尾页