*
彼はある日歯医者へ行って、奥歯を一本抜いてもらった。
舌の先でさわってみると、そこにできた空虚な空間が、自分の口腔全体に対して異常に大きく、不合理にだだっ広いもののように思われた。
……それが、ひどく彼に人間の肉体のはかなさ、たよりなさを感じさせた。
またある時、かたちんばの下駄をはいてわずかに三町ばかり歩いた。すると、自分の腰から下が、どうも自分のものでないような、なんとも言われない情けない心持ちになってしまった。
それから、……
そんな事から彼は、おしまいには、とうとう坊主になってしまった。
(大正十年二月、渋柿)
[#改ページ] *
生来の盲人は眼の用を知らない。
始めから眼がないのだから。
眼明きは眼の用を知らない。
生まれた時から眼をもっているのだから。
(大正十年三月、渋柿)
[#改ページ] *
アルバート・ケンプという男が、百十時間ぶっ通しにピアノを弾き続けて、それで世界のレコードを取ったという記事が新聞に出ていた。
驚くべき非音楽的な耳もあるものだと思う。
(大正十年三月、渋柿)
[#改ページ] *
眼は、いつでも思った時にすぐ閉じることができるようにできている。
しかし、耳のほうは、自分では自分を閉じることができないようにできている。
なぜだろう。
(大正十年三月、渋柿)
[#改ページ] *
虱をはわせると北へ向く、ということが言い伝えられている。
まだ実験したことはない。
もし、多くの場合にこれが事実であるとすれば、それはこの動物の背光性 negative phototropism によって説明されるであろう。
多くの人間の
住所では一般に南側が明るく、北側が暗いからである。
この説明が仮に正しいとしても、この事実の不思議さは少しも減りはしない。
不思議さが少しばかり根元へ喰い込むだけである。
すべての科学的説明というものについても同じことが言われるとすれば、……
未来の宗教や芸術はやはり科学の神殿の中に安置されなければならないような気がする。
(大正十年四月、渋柿)
[#改ページ] *
鳥や魚のように、自分の眼が頭の両側についていて、右の眼で見る景色と、左の眼で見る景色と別々にまるでちがっていたら、この世界がどんなに見えるか、そうしてわれわれの世界観人生観がどうなるか。……
いくら骨を折って考えてみても、こればかりは想像がつかない。
鳥や魚になってしまわなければこれはわからない。
(大正十年四月、渋柿)
[#改ページ] *
大正九年の七月に、カイゼル・ウィルヘルムの第六王子ヨアヒムが自殺をした。
ピストルの
弾が右肺を貫き、心臓をかすっていた。
一度自覚を回復したが、とうとう助からなかった。
妃との離婚問題もあったが、その前から精神に異状があったそうである。
王子の採った自殺の方法が科学的にはなはだ幼稚なものだと思われた。
なんだかドイツらしくないという気がした。
しかし、……心臓をねらうかわりに、脳を撃つか、あるいは適切な薬品を選んだ場合を想像してみると、王子に対するわれわれの感情にはだいぶんの違いがある。
やっぱり心臓を選ばなければならなかったであろう。
(大正十年五月、渋柿)
[#改ページ] *
「ダンテはいつまでも大詩人として尊敬されるだろう。……だれも読む人がないから」
と、意地の悪いヴォルテーアが言った。
ゴーホやゴーガンもいつまでも崇拝されるだろう。……
だれにも彼らの絵がわかるはずはないからである。
(大正十年五月、渋柿)
[#改ページ] *
「あらゆる結婚の儀式の中で、最も神聖で、最もサブライムなものは、未開民族の間に今日でもまだ行なわれている
掠奪結婚のそれである。……
近年まで、この風習が日本の片すみに残っていたが、惜しいことに、もうどこにも影をとどめなくなったらしい。
そうして、近ごろ都会で行なわれるような、最も不純で、最も堕落したいろいろの様式ができあがった。」
こう言ってP君が野蛮主義を
謳歌するのである。
(大正十年六月、渋柿)
[#改ページ] *
足尾の坑夫のおかみさんたちが、
古河男爵夫人に面会を求めるために上京した。
「男爵の奥様でも私たちでもやっぱり同じ女だ」といったような意味のことを揚言したそうである。
僕はこの新聞を読んだ時に、そのおかみさんたちの顔がありあり見えるような気がした。
そうして腹が立った。……
いくらデモクラシーが世界に
瀰漫しても、ルビーと
煉瓦の欠けらとが一つになるか、と、どなりたくなった。……
ヴィナスのアリストクラシーは永遠のものである。
こう言ってQ君が一人で腹を立てている。
(大正十年六月、渋柿)
[#改ページ] *
油画をかいてみる。
正直に実物のとおりの各部分の色を、それらの各部分に相当する「各部分」に塗ったのでは、できあがった結果の「全体」はさっぱり実物らしくない。
全体が実物らしく見えるように描くには、「部分」を実物とはちがうように描かなければいけないということになる。
印象派の起こったわけが、やっと少しわかって来たような気がする。
思ったことを如実に言い現わすためには、思ったとおりを言わないことが必要だという場合もあるかもしれない。
(大正十年七月、渋柿)
[#改ページ] *
寝入りぎわの
夢現の境に、眼の前に長い
梯子のようなものが現われる。
梯子の下に自分がいて、これから登ろうとして見上げているのか、それとも、梯子の上にいて、これから降りようとしているのか、どう考えてもわからない。
(大正十年七月、渋柿)
[#改ページ] *
嵐の夜が明けかかった。
雨戸を細目にあけて外をのぞいて見ると、
塀は倒れ、軒ばの
瓦ははがれ、あらゆる木も草もことごとく自然の姿を乱されていた。
大きな
銀杏のこずえが、巨人の手を振るようになびき、吹きちぎられた葉が
礫のようにけし飛んでいた。
見ているうちに、奇妙な笑いが腹の底から込み上げて来た。
そうして声をあげてげらげら笑った。
その瞬間に私は、天と地とが大声をあげて、私といっしょに笑ったような気がした。
(大正十年八月、渋柿)
[#改ページ] *
猫が居眠りをするということを、つい近ごろ発見した。
その様子が人間の居眠りのさまに実によく似ている。
人間はいくら年を取っても、やはり時々は何かしら発見をする機会はあるものと見える。
これだけは心強いことである。
(大正十年八月、渋柿)
[#改ページ] *
「三から五ひくといくつになる」と聞いてみると、小学一年生は「零になる」と答える。
中学生がそばで笑っている。
3-5=-2
[#「3-5=-2」は横組み]という「規約」の上に組み立てられた数学がすなわち代数学である。
しかし3-5=0
[#「3-5=0」は横組み]という約束から出発した数学も可能かもしれない。
しかしそれは代数ではない。
物事は約束から始まる。
俳句の約束を無視した短詩形はいくらでも可能である。
のみならず、それは立派な詩でもありうる。
しかし、それは、もう決して俳句ではない。
(大正十年九月、渋柿)
[#改ページ] *
東京へんでは、七月ごろから、もうそろそろ秋の「実質」が顔を出し始める。
しかし、それがために、かえって、いよいよ秋の「季節」が到来した時の、秋らしい感じは弱められるような気もする。
たまには、前触れなしの秋が来たらおもしろいかもしれない。
(大正十年九月、渋柿)
[#改ページ]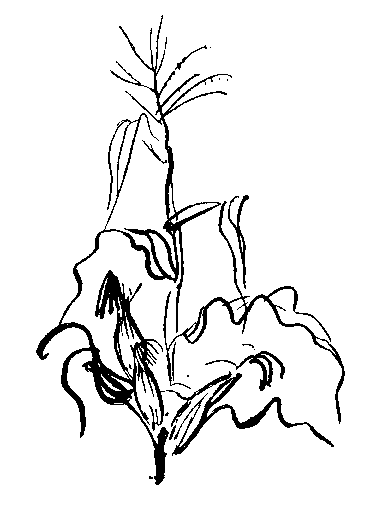 [#改ページ]
[#改ページ] *
一に一を加えて二になる。
これは算術である。
しかし、ヴェクトルの数学では、1に1を加える場合に、その和として、0から2までの間の任意な値を得ることができる。
美術展覧会の審査には審査員の採点数を加算して採否を決めたりする。
あれは算術のほかに数学はないと思っている人たちのすることとしか思われない。
(大正十年十月、渋柿)
[#改ページ] *
新しい帽子を買ってうれしがっている人があるかと思うと、また一方では、古いよごれた帽子をかぶってうれしがっている人がある。
(大正十年十月、渋柿)
[#改ページ] *
昔、ロンドン塔でライオンを飼っていた。
十四世紀ごろの記録によると、ライオンの一日の食料その他の費用が六ペンスであった。
そうして囚人一人前の費用はというと、その六分の一の一ペニーであったそうである。
今の上野動物園のライオンと、深川の細民との比較がどうなっているか知りたいものである。
(大正十年十月、渋柿)
[#改ページ] *
コスモスという草は、一度植えると、それから後数年間は、毎年ひとりで生えて来る。
今年も三、四本出た。
延び延びて、私の
脊丈けほどに延びたが、いっこうにまだ花が出そうにも見えない。
今朝行って見ると、枝の
尖端に
蟻が二、三
疋ずつついていて、何かしら仕事をしている。
よく見ると、なんだか、つぼみらしいものが少し見えるようである。
コスモスの高さは蟻の身長の数百倍である。
人間に対する数千尺に当たるわけである。
どうして蟻がこの高い高い茎の頂上につぼみのできたことをかぎつけるかが不思議である。
(大正十年十一月、渋柿)
[#改ページ] *
白い
萩がいいという人と、赤い萩がいいという人とが、熱心に永い時間議論をしていた。
これは、実際私が、そばで聞いていたから、確かな事実である。
(大正十年十一月、渋柿)
[#改ページ] *
田端の停車場から出て、線路を横ぎる陸橋のほうへと下りて行く坂道がある。
そこの道ばたに、小さなふろしきを一枚しいて、その上にがま口を五つ六つ並べ、そのそばにしゃがんで、何かしきりにしゃべっている男があった。
往来人はおりからまれで、たまに通りかかる人も、だれ一人、この商人を見向いて見ようとはしなかった。
それでも、この男は、あたかも自分の前に少なくも五、六人の顧客を控えてでもいるような意気込みでしゃべっていた。
北西の風は道路の
砂塵をこの簡単な「店」の上にまともに吹きつけていた。
この男の心持ちを想像しようとしてみたができなかった。
しかし、めったに人の評価してくれない、あるいは見てもくれない文章をかいたり絵をかいたりするのも、考えてみれば、やはりこの道路商人のひとり言と同じようなものである。
(大正十年十二月、渋柿)
[#改ページ]
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页 尾页