| 新青年傑作選(1)推理小説編 |
| 立風書房 |
| 1974(昭和49)年12月30日新装第1刷 |
| 1974(昭和49)年12月30日新装第1刷 |
序(はしがき)
聖アレキセイ寺院――。世俗に聖堂と呼ばれている、このニコライ堂そっくりな天主教の大伽藍が、雑木林に囲まれた東京の西郊Iの丘地に、R大学の時計塔と高さを競って聳(そそ)り立っているのを……。そして、暁(あけ)の七時と夕(ゆうべ)の四時に嚠喨(りゅうりょう)と響き渡る、あの音楽的な鐘声(かねのね)も、たぶん読者諸君は聴かれたことに思う。
ところで、物語を始めるに先立って、寺院の縁起を掻い摘んで述べておくことにしよう。――一九二〇年十月極東白衛軍の総帥アタマン・アブラモーフ将軍が、ロマノフ朝最後の皇太子に永遠の記憶(メモリー)を捧げたものが、このとてつもない阿呆(あほう)宮だった。そして、一九二二年十一月までが、絢爛(けんらん)たる主教の法服と煩瑣(はんさ)な儀式に守られた神聖な二年間で、その間はこの聖堂から秘密の指令が発せられるごとに、建設途上にあるモスクヴァの神経をビリッとさせる白い恐怖が、社会主義連邦のどこかに現われるのであった。ところが事態は急転して、日本軍の沿海州撤退を転機に極東白系の没落が始まり、瞬(またた)く間に白露窮民の無料宿泊所と化したのであるが、一時は堂に溢れた亡命者(エミグラント)達も、やがて日本を一人去り二人去りして、現在(いま)では堂守のラザレフ親娘(おやこ)と聖像(アイコン)を残すのみになってしまった。それにつれて、祈祷の告知だった美しい鐘声(かねのこえ)も古めかしい時鐘(ときのかね)となってしまい、かぼそい喜捨(おぼしめし)を乞い歩く老ラザレフの姿を、時折り街頭に見掛けるのであった。
さてこうして、聖アレキセイ寺院の名が、白系露人の非運と敗北の象徴に過ぎなくなり、いつかの日彼等の薔薇(ばら)色であった円蓋(ドーム)の上には、政治的にも軍事的にも命脈のまったく尽きたロマノフの鷲(わし)が、ついに巨大な屍体(しかばね)を横たえたのであるが、その矢先に、この忘られ掛けた余燼(よじん)が赫(か)っと炎を上げたと云うのは、荒廃し切った聖堂に、世にも陰惨な殺人事件が起ったからである。(読者は次頁の図を参考としつつお読み願いたい。)
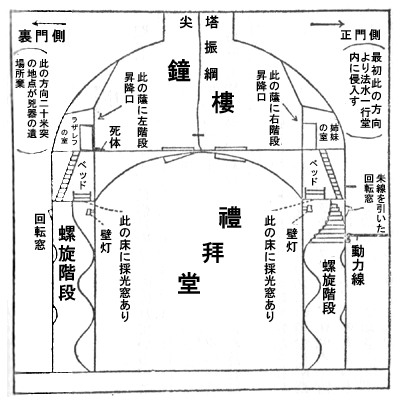
一
推理の深さと超人的な想像力によって、不世出の名を唱(うた)われた前捜査局長、現在では全国屈指の刑事弁護士である法水麟太郎(のりみずりんたろう)は、従来(これまで)の例だと、捜査当局が散々持て余した末に登場するのが常であるが、この事件に限って冒頭から関係を持つに至った。と云うのは、彼と友人の支倉(はぜくら)検事の私宅が聖堂の付近にあるばかりでなく、実に、不気味な前駆があったからだ。時鐘の取締りをうけて時刻はずれには決して鳴ることのない聖堂の鐘が、凍体(とうたい)のような一月二十一日払暁五時の空気に、嫋嫋(じょうじょう)とした振動を伝えたのである。
それも、ホンの一二分程の間で、しかも低い憂鬱な鳴り方であったが、その音が偶然便所に起きた検事の耳に入った。すると、俊敏な検事の神経にたちまち触れたものがあったのだ。と云うのが大正十年の白露人保護請願で、とりわけその中に、――当時赤露非常委員会(チェカ)の間諜(スパイ)連が企てていた白系巨頭暗殺計画に備えて、時刻はずれの鳴鐘を以って異変の警報にする――と云う条項があったからである。そこで、検事はさっそく付近の法水に電話をかけ、聖堂の前で落ち合うことになった。前日の夕方から始まった烈風交(まじ)りの霙(みぞれ)が、夜半頃に風が柔らぎ、今ではまったく降りやんだのであるが、依然厚い雪雲の層に遮(さえぎ)られて、空のどこにも光がない。その中を歩んで行くうち、ふと正門近くで法水は不思議なものにぶつかった。小さな人型(ひとがた)をした真黒な塊が、突然横町から転がり出したのである。法水がほとんど反射的に誰何(すいか)すると、その人型は竦(すく)んだように静止して、しばらくは荒い呼吸の喘(あえ)ぎが聴えていたが、やがて、つかつか前に進み寄ってきた。まず、身長三尺五寸程と思われる小児の姿が法水の眼に映ったのであるが、なんと意外なことには、次の瞬間幅広い低音(バス)が唸(うな)り出した。
「へい、私はヤロフ・アヴラモヴィッチ・ルキーン。」露西亜(ロシア)人だ――いやに落つき払っていとも流暢な日本語で、「舞台の名は一寸法師[#底本では「一寸法帥」と誤記]のマシコフと云う、寄席の軽業芸人なんで。」
「ああ、侏儒(こびと)のマシコフ!?[#「!?」は一文字、面区点番号1-8-78]」法水には、かつて彼を高座で見た記憶があった。特に強い印象は、重錘揚(じゅうすいあげ)選手みたいに畸形(きけい)的な発達をした上体と、不気味なくらい大きな顔と四肢(し)の掌(ひら)で、肩の廻りには団々たる肉塊が、駱駝(らくだ)の背瘤(せこぶ)のように幾つも盛り上っていた。年齢は法水と同様三七、八がらみ、血色のよいヤフェクト風の丸顔で額が抜け上り、ちょっと見は柔和な商人体の容貌であるが、眼だけは、切目(きれめ)が穂槍(ほやり)形に尖っていて鋭かった。
その時、二人を発見して歩み寄ってきた検事が、不意に背後から声を掛けた。
「一体こんな時刻に、どうしてこの辺を彷徨(うろつ)いているのだね。僕は地方裁判所の検事なんだが。」
「実は、飛んだ罪な悪戯(いたずら)をした奴がおりましてな。」不意を喰って愕然(ぎょつ)と振向いた態(かたち)のままで、ルキーンは割合平然と答えた。
「皇帝(ツァール)への忠誠一筋で、うっかり偽電報を信用したばかりに、あたらの初夜を棒に振ってしまいましたよ。」
「初夜!?[#「!?」は一文字、面区点番号1-8-78]」検事は唆(そそ)られ気味に問い返した。
「さよう、不具者(かたわもの)の花嫁は、ここの堂守ラザレフの姉娘ジナイーダなのです。無論われわれには式なんぞありませんが、いよいよ最初の夜が始まろうと云う矢先でした。かれこれ十一時頃だったでしょうか、皮肉なことに、突然同志から電報が舞い込んできて、二時までに豪徳寺駅付近の脳病院裏へ来い――と云います。しかし、結局私には、寝室の歓楽よりも同志の制裁の方が怖ろしかったのです。それで、厭々(いやいや)出掛けましたよ。」
「同志とは?」検事は職掌柄聴き咎(とが)めた。
「新しい白系の政治結社です。それに、レポとしての私の体(からだ)には、先天的に完全な隠身術が恵まれています。これは公然(おおびら)に申し上げてもよいことでしょう。」ルキーンは傲然(ごうぜん)と志士気取りに反(そ)り返った。「何しろ、お国のある方面から非常な援助を頂いているのですからなア。怖ろしいのはGPU(ゲーペーウー)の間諜網だけですよ。」
「なるほど、トロツキーが驢馬(ろば)の脳髄と云っただけのことはあるね。」法水が皮肉に笑うと、ルキーンはちょっと厭な顔をしたが、先を続けた。
「ところがどうでしょう。霙の中に二時間余り曝(さら)されていても、脳病院の裏には人っ子一人来ないのです。そこで始めて、あの電報が、私の幸福を嫉(そね)んだ悪党の仕業だったと云うことが判りました。そして、歩いて帰るよりほかに方法がなくなってしまったのです。」
「しかし、君はそんなに疲れている癖に、現在僕の前へは鉄砲玉のように飛び出したじゃないか。」法水は叩きつけるような語気で云った。
「鐘の音を聴いたからです。われわれの同志の間では、刻限はずれの鐘を変事の警報にしているのです。」ルキーンは身体(からだ)を焦(いら)だたし気にもじらせて、声を慄(ふる)わせた。「鳴ったと思うとすぐやんでしまったのと云い、あの弱々しい音を考えると、なんだか私には、鐘の振綱に触れた手を、理不尽に横合いから遮られたような気がするのです。つまり、すでに行われた変事の発見ではなくて、異変の進行中に鳴らされた救助信号ではないかと思うのです。しかも、それ以前に私は、偽電報で釣り出されています。」
「行こう」検事はたまりかねて叫んだ。「なるほど、鴉(からす)や鳶(とび)ぐらいでは、あの鐘はビクともしないぜ。」
不思議な侏儒(こびと)ルキーンの出現は、それまで多寡(たか)を括(くく)っていた、法水の鐘声に対する観念を一変させた。そして彼は、凄惨な雰囲気の中に、一歩踏み入れたような気がした。…少なくとも、鐘声と一寸法師[#底本では「一寸法帥」と誤記]とが偶然の逢着でさえなければ、因果関係の結論として、いかなる形体(かたち)にせよ、聖堂の中へ残されたものがなければならない。凍った地面がバリバリ砕けて、下の雪水が容赦なくはねかかった。やがて、幾百と云う氷柱(つらら)で薄荷糖(はっかとう)のように飾り立った堂の全景が、朧気(おぼろげ)に闇の中へ現われた。
出入口の把手(ノッブ)を捻(ねじ)ってみると鍵が下りているので、ルキーンは検事を振り仰いで、
「一つ、そこに下っている綱を引っ張ってみて下さい。それで鳴る鳴子(なるこ)が親爺(おやじ)の方にも娘の方にも、両方の室にあるのですから。」
ところが、検事が懸命に引く鳴子に対して、内部(なか)から誰一人応ずるものがない。そのくせ、内部で鳴っている音が、戸外(そと)にいる彼等にも判然と聴き取れるので……、今か今かと待つうちにも、よほどの時間が経過してしまった。
「ただごっちゃないぞ。」奥歯をギリリと鳴らして、検事が綱から手を放すと、その手に法水は合鍵の束を与えた。そして、七本目がようやく合って、扉(ドア)が開かれた。
法水の細心な思慮は、いち早く階段を駈け上ろうとする二人を引き止めて、まず検事に、今入った入口の扉際で張り番をさせ、自分はルキーンを伴って、階下の室々を調べ歩いた。荒れるに任せた礼拝堂は、廃墟のような風景であった。円天井(まるてんじょう)の下には、十ばかり聖像(アイコン)があるのみで、金色燦然たる天主教の聖器類は影も形もなく、装飾箔を剥がした跡さえ所々に残っていた。法水の調査は、便所と急造の炊事場を最後に終ったが、どこにも人影は愚か、異状らしい個所は発見されなかった。
検事のいる扉際に戻ると、法水は鐘楼に出る左側の階段を上り、検事とルキーンは右側のを上って行った。
「これが解せないのですよ。」緩く迂回(うかい)しながら伸びている階段の中途の壁に、点(つ)け放しになっている壁燈(かべあかり)を見て、ルキーンが云った。「戸外(そと)から見た時、明るい窓が一つあったでしょう。それがこっち側の回転窓を通して見た、この壁燈の光なんです。点(つ)け放しなんて――こんなことは、ラザレフの吝嗇(けちんぼ)が狂人にでもならなけりゃ、てんでありっこないのですがね。」
その時、検事がルキーンの袖を引き、無言で天井の床を指差した。そこには硝子(ガラス)窓の明り取りが開いていて、背の高い検事には、そこから、静止している二人の女の裸足が見える。寝台にならんで腰を下しているらしい。ルキーンは二三段跳び上って、
「アッ、影が動きましたぜ。してみると、姉妹には別条ありません。ヤレヤレ、飛んだ人騒がせだったぞ。いや、たぶん鐘声などにも、案外下らない原因があるのかもしれませんよ。」
「それにしても、起きているくせに、さっきはどうして応(こた)えなかったのだろう。」検事は腑(ふ)に落ちぬらしく呟(つぶや)いたが、ルキーンはなぜか急に当惑気な表情を泛(うか)べて、答えなかった。
鐘楼はまったくの闇だった。上方から凍えた外気が、重たい霧のように降(ふ)り下って来る。二人の前方遙(はる)か向うには、円形の赭(あか)い光の中に絶えず板壁の羽目が現われて、法水の持つ懐中電燈が目まぐるしい旋回を続けていた。それがようやく一点に集注されると、ルキーンはアッと叫んでドドドッと走り寄った。半ば開かれた扉の間に、長身痩躯(そうく)の白髪老人が前跼(まえかが)みに俯伏(うつぶ)して、頤(おとがい)を流血の中に埋めている。
「ああ、ラザレフ!![#「!!」は一文字、面区点番号1-8-75]」ルキーンはガクッと両膝を折って、胸に十字を切った。「フリスチァン・イサゴヴィッチ・ラザレフが……」
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页 尾页